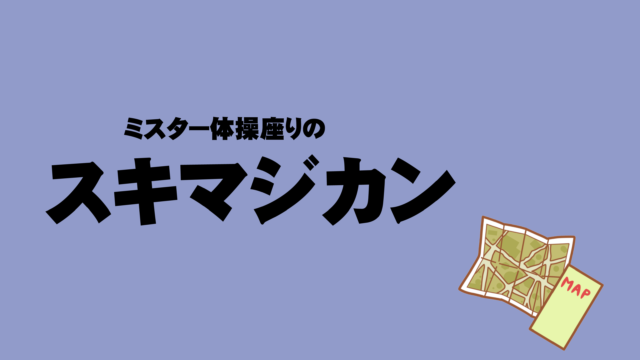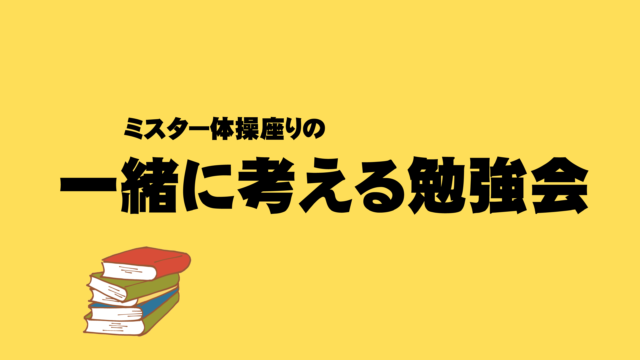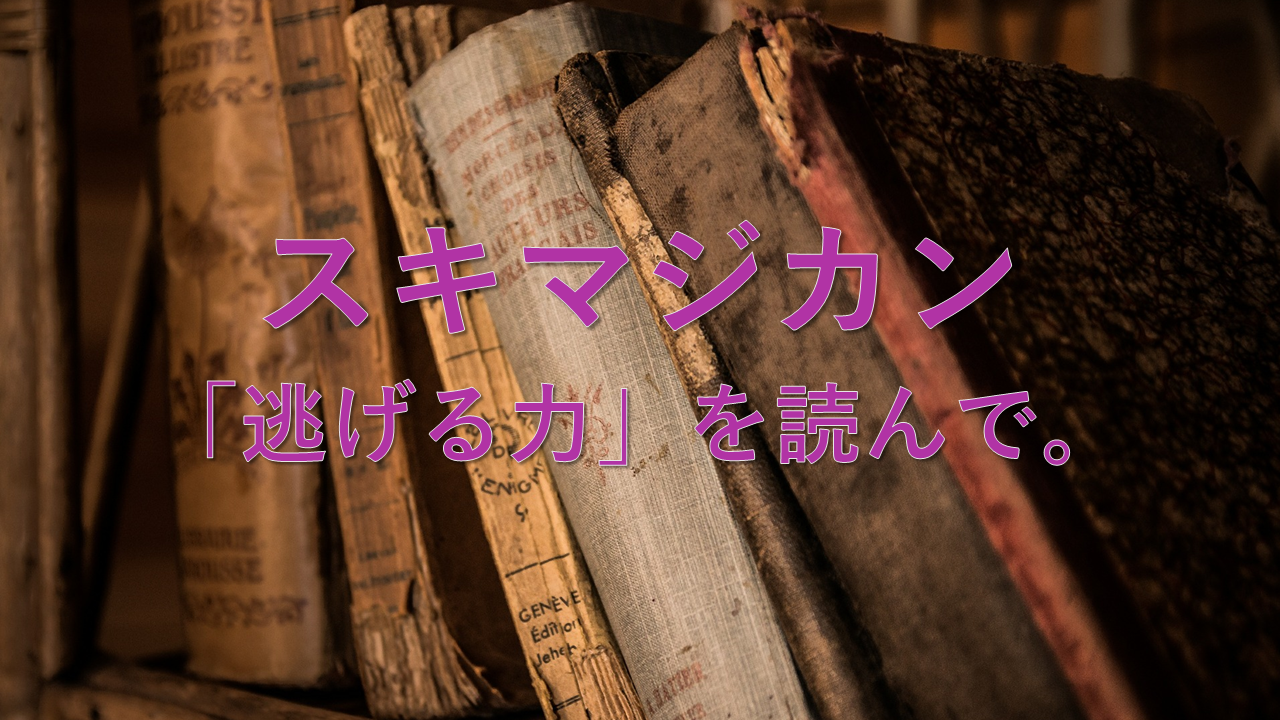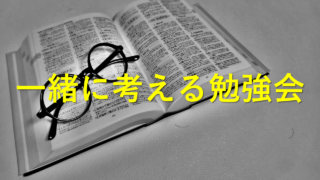現代は鬱・ストレス社会なのか?
この本を選んだ理由は2019年度に、大洲青年会議所が地域の課題として「鬱・ストレス」等によるひきこもりをテーマに事業を展開したいと思っていたからです。
さて、小さな会社を経営しているのですが、今のスタッフがどれだけ会社に対してストレスや不満を持っているのかというのは気になるところ。昨年、高卒の新入社員を雇用したのですが1年で辞めてしましました。いや、これは実は気づかないうちに会社が当人に何らかのストレスを与えてしまい辞めさせてしまったのかもしれません。今回は自らが追いかける夢を諦めたくないとの理由で弊社を退社しました。さらに、私にはまだ子供がいませんが、将来子供が学校や友達関係で鬱が原因でひきこもりになったりする可能性はゼロではないのでそのあたりも気になるところ。今のうちに勉強をしたいという気持ちでテーマを選出を。
逃げる力とは?。
これは、ひきこもりとか鬱とかの問題の本?。
てなわけで、世の中にはいくら文句を言われようがストレスを全く感じない人と、そんなに強くは言われていないのにスグにストレスとして嫌な思いを抱え込んでしまうタイプの人間がいると思います。パターンをあげると他にもあるけども。あなたはどちらタイプでしょうか?私はどちらかと言うと何かを言われたり体験したその瞬間はストレスをためるかもしれませんが、寝たら忘れるそこまでは抱えない人間だと思ってます。いや、思い込んでます。
ひきこもりとは(厚生労働省の定義)
仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人との交流をほとんどせずに6か月以上続けて自宅にひきこもっている状態」
ここでの驚きは6か月以上と期限が定められているということと、交流をほとんどせずということなので家から少しコンビニへ行ったりレンタルショップへ行けたりする人も引きこもりと定義づけられるということ。現在では10代だけでなく20代、30代、40代でも珍しくはないそうです。
では、この本の一説をお借りします。
「ひきこもり」は正しい「逃げ」か
野生動物もケガをしたときは傷が癒えるまで穴などに入ってひたすらじっとしているように、人間も会社や学校などで精神的に大きな傷を負い、休養が必要になったら、体力が回復するまで、ひきこもっても良いと思います。
しかし、野生動物は傷が癒えたら穴から飛び出していく。
難しい問題には踏み込んでいませんがひきこもりについても様々な角度から書いています。
また、様々なテーマをピックし作者の「逃げる力」に対する価値観で書いていました。
同じ気を使うのならば自分の価値を大事にする人間
逃げることも勇気を持つ
負けないような逃げ方を考える
しっかりと守るべきものはブレない人間
こんな、じいちゃんカッコいい。ちゅーす。
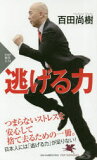
◆◆逃げる力 / 百田尚樹/著 / PHP研究所