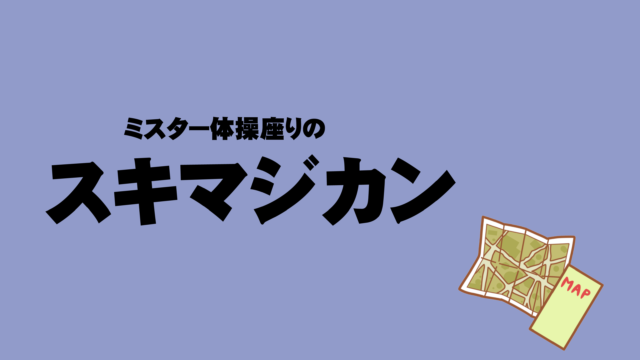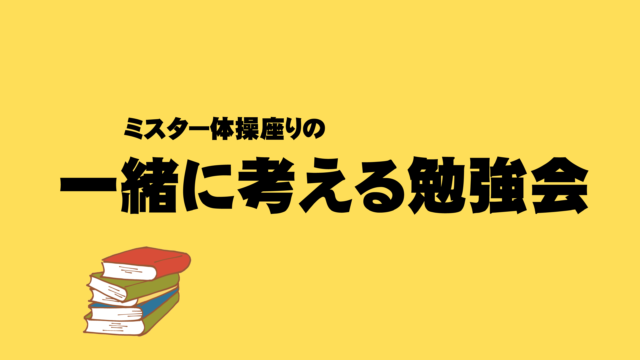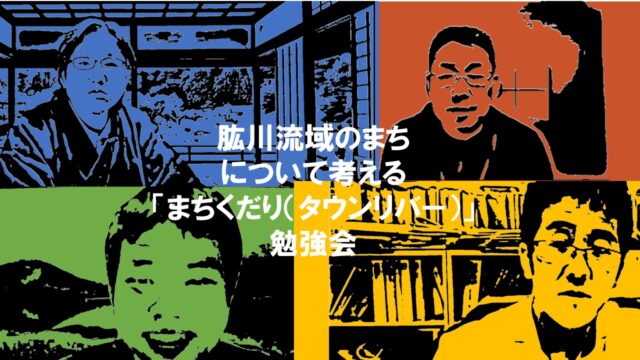思い返しても、ありゃ周りがいたからできてたな。
地元の仲間や協力してくれる方との時間(毎年数か月の準備期間とイベント当日)をかけ、次から次へと出ていく出費で学べたことは、イベントごとの収支決算、スポンサー企業集め、グッズ制作と販売、コンテンツ作り、広報、企画運営、協力者との連携、地元への理解と経験できた。20代前半から全く儲からないイベント制作会社みたいな経験は「稼ぐことの大切さ」「イベント主催者の苦労」「継続するための労力」を学ぶ事ができました。田舎を盛り上げたい思いで始めたけども、終わってみるとあっけなく、主催側である僕たちが改めて地元の事を好きになることができました。きっと同じような思いで都会から帰る田舎者の皆さまにエールを送りたい。
この記事は連続する5つの記事の5本目です。まだ最初から読まれてない方はそちらからお読みください。
10年間だけ地元の野外イベント運営してきたのでそのノウハウと反省点の話をしようかな。その1
目次
もっかい初めからできるなら
どんなカタチでも開催できてたので大きくは変えないだろうな。「大きくしない」ってことは今からやっても心がけるかなと思います。あとは作り上げていくところから情報発信もしてきたけども、使用しているSNSには限りがあったので今ならばプレスして、マスコミの力を利用するだろうな。あとはバズの可能性もあるTwitterなども駆使して発信するだろうな。あまりフォロワー数には注目してこなかったけども、マーケティングとしてフォロワーの水位なども追いかけたいところ。また、分かり切っていたターゲット=地元の小学生、中学生、高校生への直接的な情報発信のために教育委員会にも後援についてもらって資料配布なども依頼するだろうな。後継者を育成しようと色んな人に役割分担したけども、どの部分を任せるかは明確にさせるだろうな。やはりボランティアの範囲とビジネスの範囲を分け過ぎたので、もっと負担がかからないような仕組みで、仕事の一環としても活動できるようなマネタイズ方法をもう少し初期の頃から構想するだろうな。自分のお金でやらないってことを心がけると思います。
誰でも挑戦できる環境づくり
挑戦する人の背中は押していくこと。田舎ってすごく挑戦しやすいハード環境はそろっているのに、ソフト環境が問題になる時もありますよね。昔ながらのやり方を守る人と新しいことを始めたい人の葛藤っていうのはなくならないんだろうな。なんて話をしながら、それでも話をするだけでも実は広がるかもしれない。と次の僕たちの課題やステップも見えてきました。学校訪問だけでなく多くのカタチで伝えて、地元の若い子たちには人生を楽しんでもらいたいです。
①とりあえずやってみる。
②とりあえず周りにやりたいって言ってみる。
みんなで振り返ってみた。
この記事を書いていたから集まって話を聞いてみようかなーと思い企画した時の様子です。最後までまだ編集はできていませんが、結果がどうであれこのメンバーでやってたから楽しかったんだろうなと僕は思いました。内容が全くない短編集動画がこれから少し続いていきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。地域を盛り上げたい気持ちに素直に向き合って、どんどんみんなで実験に実験を重ねて爆発させていきましょう。これは、祭りである。