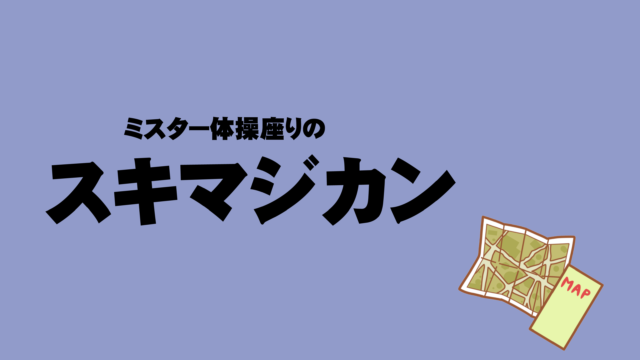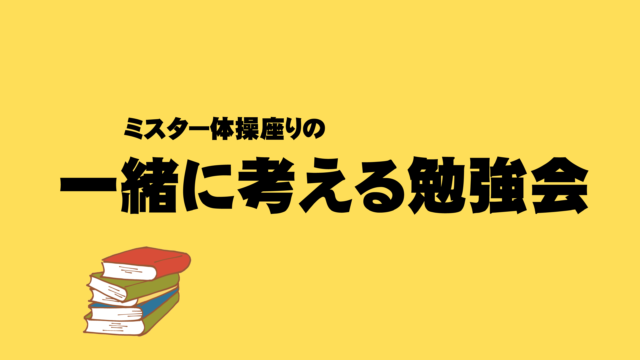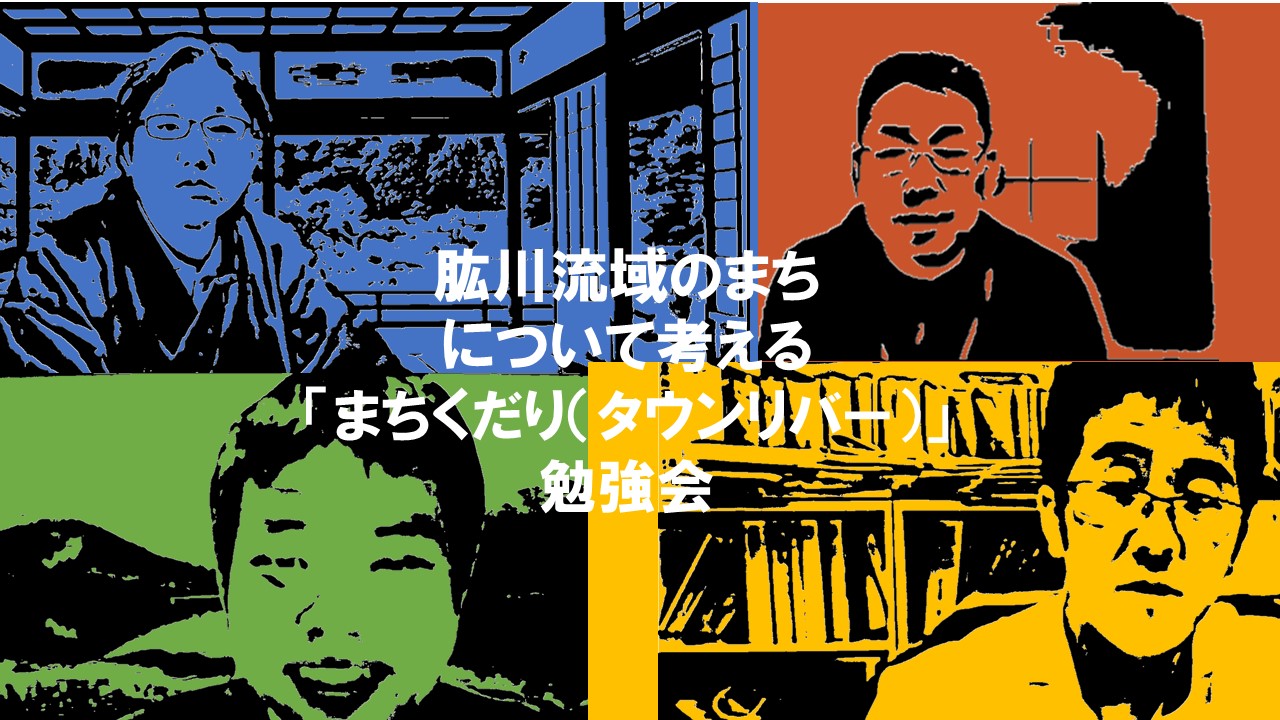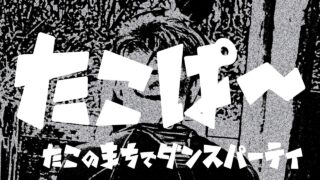いつも歩く道のり、見慣れた路地、風景。そんな日常生活の中で、「あの施設って何だろう?」「あの会社って何してる会社だろ」とふと思うコトってよくありませんか?見慣れ過ぎていて意識していなかったけど、実はとんでもない施設やったんや!なんて経験。今回の内容はダムについてです。雨が降ると大量の水が川に流れちゃうから、それを調整するためにダムってあるんじゃないの?と思っていましたが、ダムがあるとないとではどのように下流では水量が異なるのかなどを学びました。防災減災と密接に関係するテーマです。一緒に考えていきましょう!これから地域の勉強会を主催される方も参考にしてみてはいかがでしょうか。
この記事は全5回になる記事の5本目です。まだ1本目を読まれていない方はそちらからお読みください。観光について学んだ会ですのでお楽しみに。wikioediaによるとダム(英: Dam)または堰堤(えんてい)は、水力発電や治水・利水、治山・砂防、廃棄物処分などを目的として、川や谷を横断もしくは窪地を包囲するなどして作られる土木構造物。一般にコンクリートや土砂、岩石などによって築く人工物を指す。大規模なダムで川を堰き止めた場合、上流側には人造湖(ダム湖)が形成される。日本国内に建設され管理・運用されているダムについて、特に治水・利水を目的としたものを中心に扱うそうです。防災のためのダムとはここ最近言われ始めているみたいですね。
目次
大洲市のダム専門家による勉強会

国土交通省肱川ダム統合管理事務所鹿野川ダム管理支所支所長の井上博文さんからは、減災のためのダムの利用、そして平成30年7月豪雨以降にできたユニバーサルデザインを取り入れた伝わる防災方法についてお話をいただきました。
地域/ダムを理解する
肱川は勾配が少なく土地が隆起してできたため大量の雨が降ってしまうと抜け場がなくなり氾濫が起こりやすい河川です。平成30年7月には豪雨による被災もありました。全国と比べて肱川は、一級水系(※いっきゅうすいけいとは、河川法に定められた日本の水系の区分により、国土交通大臣が国土保全上または国民経済上特に重要として指定した水系のことです。「河川法第四条第一項の水系を指定する政令」に基づき、全国で109水系が指定されています。)にも関わらず、堤防の整備率が低いです。まだまだ出来上がっていない河川だと言えるそうです。
鹿野川ダムは洪水調節や発電のために建設されたが、一級河川にもかかわらず整備などが十分に出来上がっていない環境では、下流に対して万能で無限に効果を発揮できるものではありません。しかし出水に対してなどダムがないよりはある方が確実に良く、ダム管理者は住民の安全のためにも可能な限りダムを有効に使用したい気持ちで日々業務をされています。

持続可能な仕組みを構築していく
![]()
![]()
![]()

これまでの周知方法からユニバーサルデザインを取り入れた伝わる周知方法へ切り替えています。方法は、各所にランプを設け色ごとに現在の危険度が知れる方法です。広報誌による周知を引用していますのでご一読お願いします。全国的にも先駆けた取組みだそうなのです。みんなが理解することでより高い効果を発揮します。正しく恐れ、正しく理解し、正しく行動ができるためにも、出水に対する周知方法の理解などを伝えられる地域の大人の存在が不可欠ですね。

【引用:広報おおず2020年4月号】
何かつかめましたか
危機感を持ち、そして青年会議所への強い思いも持ちながら井上さんはお話をされていました。ちゃんと自分たちなりに調べて、きっちりと理解もすること。そしてしっかりと学んだことを多くの方に伝えていくことこそが防災や減災にも繋がって、強い地域になるのだなとお話を聞いて思いました。ダムの話でしたが、防災減災に関わる内容でした。個人でもグループでも企業でも防災減災について関われる事で地域は強くなると考えます。一緒に地域にインパクトを与えていける存在になりましょう!最後までお読みいただきありがとうございます。それぞれの記事もお読みいただけると理解も深まりますのでお願いします。この記事は全5回になる記事の5本目です。まだ1本目を読まれていない方はそちらからお読みください。